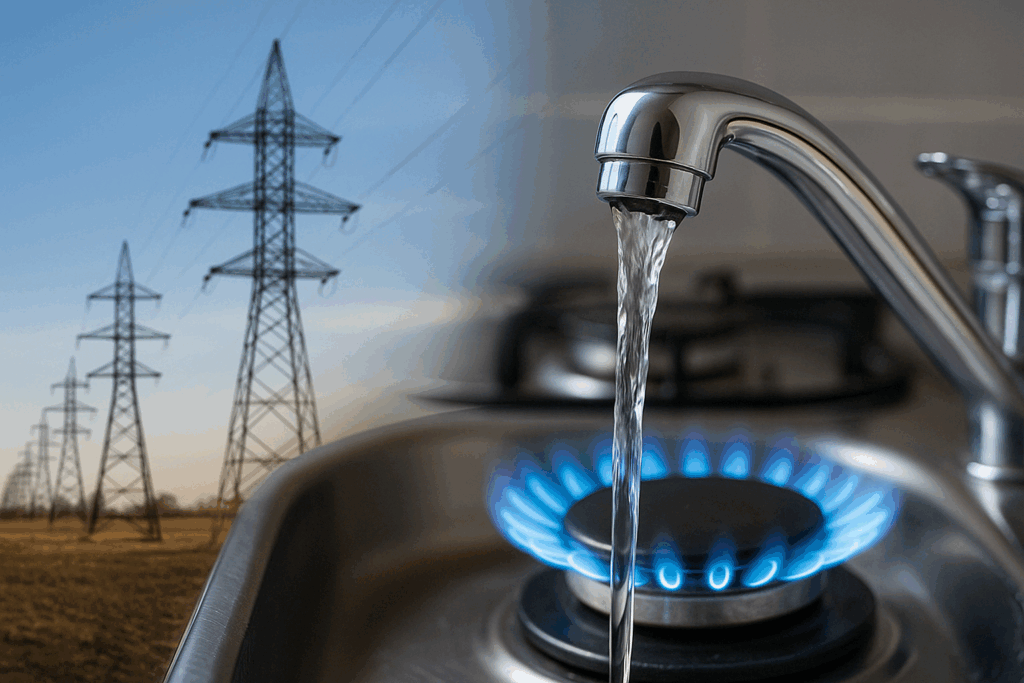※営業やご提案は受け付けておりませんので、ご遠慮ください。
受付時間 8:00〜17:30

トレーラーハウスとは、車で移動・移設できる小さな家のことです。厳密には、日本においてトレーラーハウスは建築基準法における「建築物」とみなされていないため、「家」ではなく、”住むことができる車”、つまり「車両」として扱われます。
タイヤのついたシャーシの上に建物が乗っている形態で移動できるのが特徴で、キャンピングカーは牽引して使用するのに対し、トレーラーハウスは移動はできるものの、使用時は一定の場所に設置します。
電気やガスなどの配線・配管についても設置可能で、用途によって違いはありますが、キッチンやリビング・寝室・シャワールームなどが設置されているものもあり、レジャー・別荘・店舗などに利用されることが多いです。
なお、前述の通りトレーラーハウスは「建築物」ではなく、「車両」として扱われるので、固定資産税がかからない代わりに、道路交通法による規制を受けることになります。
こちらのタイプのトレーラーハウス(7.2mサイズ)なら
530万円でご購入いただけます。
もちろん、お好みにカスタマイズすることも可能です。
トレーラハウスは下記の二種類に分類されます。
「道路運送車両の保安基準」で定める車両(車幅2,500mm未満、車高3,800mm未満、車長12,000mm未満)で自動車として認められているもの。


車幅2,500mm以上、車高3,800mm以上、車長12,000mm以上の車両で運輸局に「基準緩和の認定」を申請し、認定を受けたのち2カ月間のみ通行できるようにしたもの。
認められれば、「車輪を有する移動型住宅で、原動機(エンジンなど)を備えず牽引車により牽引される」トレーラーハウスであり、
自動車であって建築物ではないことになります。
なお、「随時かつ任意に移動できる」かどうかを判断するのは誰かと言うと、
各自治体の建築主事(建築確認申請を審査する担当者)が判断します。
上記では「道路運送車両の保安基準」という法律の話でしたが、
置いて継続的に利用する場合は「建築基準法」が判断基準になります。

トレーラーハウスは、基本的に移動が可能な場所であればどこでも置くことが可能です。
建築物ではないので、市街化調整区域にも置くことができます。
注意が必要なのが、設置場所までの道路幅です。建築物と違い「随時かつ任意に移動できる」ものがトレーラーハウスであるため、設置場所までの道路を通行できないようなトレーラーハウスは設置することができません。
同様に、自宅の庭に置く場合、道路から庭へトレーラーハウスが出入りできないとトレーラーハウスを設置することができません。
トレーラーハウスを牽引する場合、免許を取るか、免許を持つ業者に依頼することになります。
牽引免許が必要になり、その牽引免許を取得するには牽引する車の種類に応じて普通免許や中型免許等が必要になります。
牽引免許は必要ありません。

自治体にトレーラーハウスを車検付きの車として認められれば、もちろん固定資産税等は不要です。
代わりに通常の車と同様、自動車取得税や自動車重量税、自動車税が必要になります。
※税額については購入したトレーラーハウスの金額やサイズ等によって異なります。
一方で、サイズが大きいなど「車両ではないけれど『基準緩和』を申請すれば道路を走れるトレーラーハウス」の場合、現在のところ税金に関する法律等がなく、グレーゾーンになっています。一刻も早い法整備が望まれています。
トレーラーハウスには電気・ガス・水道といったライフラインを接続することができます。
ただしトレーラーハウスが車両か建築物かの判断基準の一つに、こうしたライフラインの配線や配管などが「工具を要さずに取り外すことが可能」かどうかがあります。
トレーラーハウスなどの車両の建築基準法上の取り扱いについては、平成25年(2013年)に日本建築行政会議が発行する基準総則の「車両を利用した工作物」の欄に定められました。ここには、給排水やガス、電気などの設備配線や配管が簡単に取り外せないものは、建築物として取り扱うとしています。 しかし、都市計画法ではトレーラーハウスについては触れられていません。そのため、多くの自治体ではトレーラーハウスを「車両」として扱うか「建築物」とするか苦慮しているのが実情です。
あまりよく理解せずに大丈夫だろうと安易に置いた後に、自治体から撤去を命じられたケースも実際にあります。
自治体に相談すれば解決するかといえば、自治体もトレーラーハウスの扱いに苦慮しているところが多いのが現状です。
トレーラーハウスを購入して設置したいのであれば、まずは全日本トレーラーハウス組合に加盟している当社に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。